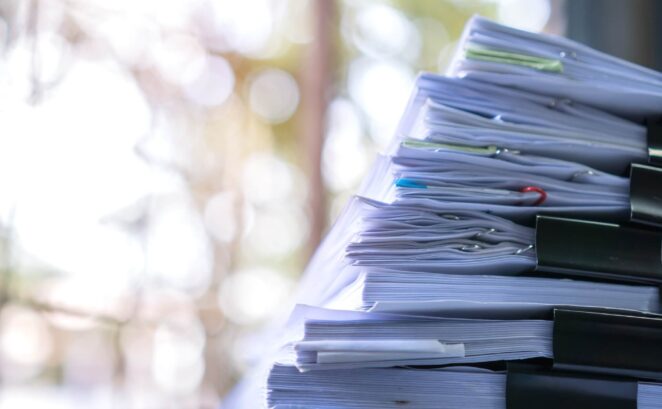2021.04.21
前十字靭帯損傷
前十字靭帯再建手術後は筋力だけでなく、動きの”質”まで回復させる
執筆中尾 優作(理学療法士/プロスポーツトレーナー)
ヨーロッパの大学、大学院で理学療法を学ぶ。欧州サッカー、日本のB.LEAGUEでトレーナーとして活動したのち、地元神戸三宮にメディカルフィットネスジム【Lifelong】を設立。トップアスリートを始め、"病院で治らない痛み"に悩む人にワンランク上のリハビリを提供する。

日本語では、”前十字靭帯再建手術後に両脚の非対称性を明らかにするための機能的なデータ分析の実用性”となります。
直訳すると難しい単語が並びますが、結論をまとめると「前十字靭帯の手術後に手術していない側の脚と同じくらい筋力が回復して跳べるようになっても、動きの”質”まではすぐに回復しない」ということを発表した論文になります。
論文の目的
この論文の著者であるミシガン大学のMcKenzieさんたちは前十字靭帯の再建手術を受けてスポーツ復帰するときに、現在広く使われているトリプルホップテストというテストの結果を指標に競技復帰しても本当に大丈夫なのか?と考えたようです。
トリプルホップテストというのは片足で3歩前に連続で跳び、3歩合計の距離を測ります。
手術をした脚が健常な脚の90%以上跳べるようになったら筋力は十分に回復していると考えられ、競技復帰の目安の一つとして使われています。
検証方法
実験の被験者は過去に前十字靭帯再建手術を受けたことがあり、トリプルホップテストで健側の90%以上の結果を出すことのできた15名と今まで下肢の手術を受けた経験のない15名。
両者にトリプルホップテストを行ってもらい、3歩のホップのうち2歩目の着地をフォースプレートという器具で地面への力の伝わり方を計測します。
同時に身体には37個のマーカーを付け、モーションキャプチャーで関節の動きも測定します。
測定結果は以下のように比較されました。
- 再建手術をした脚と同じ人の再建手術をしていない脚
- 再建手術をした脚と下肢の手術を受けたことのない人の脚
実験結果
顕著に現れた結果は、着地の瞬間に起こるイーセントリック収縮時に、前十字靭帯再建手術を受けた側の膝が発揮する力が低く、足首と股関節が発揮する力が高かったようです。
この結果から考えられることは、手術を受けた膝は力を入れにくい状態が残っていて、膝をかばうために足首と股関節が替わりに頑張っているということです。
今回の被験者はトリプルホップテストで左右差がほとんどないという結果を出しています。
例えば健側で3mを記録したとしたら、手術を受けた脚の記録は2m70cm以上跳べていることになります。
このテスト結果だけを見ると左右差はほとんどなく、練習に復帰しても大丈夫だろうと考えることができます。
しかし、実際にそのホップの”質”という部分に注目してみると、膝の発揮する力は左右差が残った状態だということがわかりました。
考察
今回の論文が明らかにした内容は、前十字靭帯再建手術を受けたスポーツ選手が練習に復帰するまでに、今まで以上に気をつけなければいけないと注意喚起しています。
手術後に競技復帰にしようとしてよく使われるのは、筋力やホップの距離などの数字ですが、その数字を出すための動き自体が正しく、質の良い動きでできているかということも大事だということです。
研究結果では着地時のイーセントリック収縮時に膝の力発揮が低下していることがわかりました。
このイーセントリック収縮が起こるのは、ホップやジャンプの着地時だけでなく、ストップ動作でも起こります。
イーセントリック収縮時の筋肉は非常に大きな筋出力を行うので、これらの動作中に関節運動を適切にコントロールすることは非常に重要です。
前十字靭帯の怪我は再発率も高く、着地やストップ動作は再受傷リスクの非常に高い動きになるので、いかに動きの質を高めることができるかが、再発予防にも大きく関わってきます。
前十字靭帯損傷に関してはこちらのページにより詳しくまとめてありますので、ぜひご覧ください。
前十字靭帯のリハビリメニューをお探しの方はこちらの記事をご覧ください。
他の前十字靭帯に関する医学論文は、こちらのページにまとめてあります。
>> 前十字靭帯に関する論文紹介まとめ
関連する記事
-
2024.10.18
前十字靭帯再建手術から9ヶ月以内に競技復帰すると、再受傷リスクは7倍に
-
2024.10.01
前十字靭帯に関する論文紹介まとめ
-
2024.09.27
前十字靭帯に負荷をかける筋肉と負荷を下げる筋肉